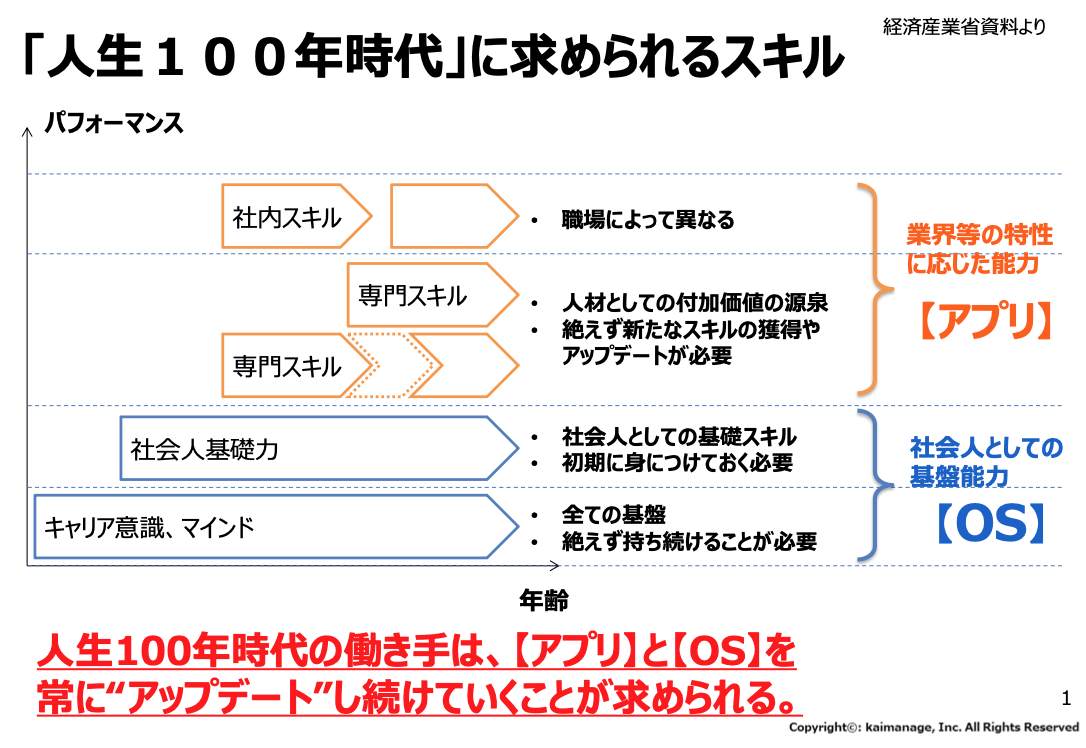セルフケアはOS
まず、ラインケアや両立支援は“寄り添い”のように見られがちです。
それも否定しませんが、じつは別ものと考えており、
「職場では医療的ケアはできない」という原理原則のもと、
求められているのは、”法的責任と合理的配慮に基づく判断力”
と考えられます。
ラインケアとセルフケア、も別ものと考えてます。
ラインケアは、職場が担う“労務的な対応”
・業務に必要なコミュニケーション
・業務に支障が出ている社員に同じ指示が続く場合は、
人事や産業医に共有し健康チェック
(部署や上司が業務以外の判断をしない)
・就業可否などの判定
セルフケアは、本人が担う“自己管理スキル”
・自己保健義務あるが罰則なし
・やってもやらなくても良い福利厚生的
・やったほうが圧倒的にお得→セミナーで育生
職場で求められる業務に必要なテクニカル・スキルを”アプリ”とすると、
セルフケアは、アプリ以前の“OS”にあたります。
社会人としてのスキルや、テクニカル以前の自己管理スキル。
これは、ケアというより、”セルフ・マネジメント”と表現した方が適切かもしれません。
セミナーで、このような区別で話しますと、「腑に落ちた」と良い評価を頂きます。
実はこのような視点で語られることは、あまりありません。
私のセルフケア提案は、医療的アプローチ以前の“誰もができる生活習慣のコツ”。
うつ状態で、”何もできない状態”でさえ、すぐできる内容にまとめてあります。
それがそのまま、習慣の見直し〜認知の変容〜再発防止の要素をも含みます。
多くの疾患の治療方針ともバッティングせず、むしろ回復を支えるベースになります。
治療なしで改善するケースすらあります。
だからこそ、セルフケアは、職場でもとめられる各種能力(OS、アプリ、NTS)を
発揮するための、基盤中の基盤、つまりOSなんです。
それも否定しませんが、じつは別ものと考えており、
「職場では医療的ケアはできない」という原理原則のもと、
求められているのは、”法的責任と合理的配慮に基づく判断力”
と考えられます。
ラインケアとセルフケア、も別ものと考えてます。
ラインケアは、職場が担う“労務的な対応”
・業務に必要なコミュニケーション
・業務に支障が出ている社員に同じ指示が続く場合は、
人事や産業医に共有し健康チェック
(部署や上司が業務以外の判断をしない)
・就業可否などの判定
セルフケアは、本人が担う“自己管理スキル”
・自己保健義務あるが罰則なし
・やってもやらなくても良い福利厚生的
・やったほうが圧倒的にお得→セミナーで育生
職場で求められる業務に必要なテクニカル・スキルを”アプリ”とすると、
セルフケアは、アプリ以前の“OS”にあたります。
社会人としてのスキルや、テクニカル以前の自己管理スキル。
これは、ケアというより、”セルフ・マネジメント”と表現した方が適切かもしれません。
セミナーで、このような区別で話しますと、「腑に落ちた」と良い評価を頂きます。
実はこのような視点で語られることは、あまりありません。
私のセルフケア提案は、医療的アプローチ以前の“誰もができる生活習慣のコツ”。
うつ状態で、”何もできない状態”でさえ、すぐできる内容にまとめてあります。
それがそのまま、習慣の見直し〜認知の変容〜再発防止の要素をも含みます。
多くの疾患の治療方針ともバッティングせず、むしろ回復を支えるベースになります。
治療なしで改善するケースすらあります。
だからこそ、セルフケアは、職場でもとめられる各種能力(OS、アプリ、NTS)を
発揮するための、基盤中の基盤、つまりOSなんです。