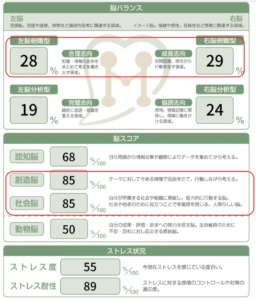社会脳テスト:”問題解決”に慣れた脳
職場でこんなシーン、見かけたことはありませんか?
「もっと良くしていくには?」「ありたい姿は?」
と聞かれて、急に言葉に詰まる上司。
それは決して、能力ややる気の問題ではありません。
実はその反応、“脳の使い方のクセ”が関係しているのです。
社会脳テストでは、人によって使い慣れている脳の傾向が見えてきます。
特に、
・左脳俯瞰型(目的・論理を重視)
・右脳分析型(他者の評価や成果への意識が強い)
この2つが高い方は、
「何が問題か」「目的に沿っているか」といった明確でロジカルな判断軸に強く反応します。
一方で、以下のような問いに対しては、脳が動きにくくなる傾向があります。
「もっとよくするには?」
「このチーム、今どんな空気?」
「ありたい姿って、何だろう?」
答えのない問いに対して、戸惑いや苛立ちを覚えるのは自然なことです。
それは、普段の業務が「正解のある課題」に慣れすぎているからかもしれません。
そんなときに有効なのが、脳の柔軟体操です。
・感じたことを、あえて言葉にしてみる
・正解のない問いに向き合ってみる
・共感や違和感など、場の感性を拾ってみる
はじめは抵抗があるかもしれませんが、
続けていくうちに、論理以外のアンテナも立ち始めてきます。
この脳のバランスを知ることは、
ビジョンづくり、心理的安全性、創造性など、
これからの組織運営に欠かせないテーマと深く関わっています。
正解のない問いに、立ち止まらずに向き合える人を育てること。
それが、これからのマネジメントや人材育成において、重要な視点です。